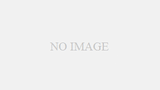歯磨きのときに歯ぐきから血が出ると、「大丈夫かな」と不安になりますよね。もしかしたら、「いつものことだから」と軽く考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯ぐきからの出血は、お口の中や体の健康状態が悪くなっていることを知らせる大切なサインである可能性があります。
この記事では、なぜ歯ぐきから血が出てしまうのか、その主な原因をわかりやすく解説します。また、ご自宅で今日からできる効果的なケア方法や、歯科医院を受診すべきタイミングについても具体的にご紹介します。専門的な言葉は避け、初めての方でも理解しやすいように説明いたしますので、この記事を読んで、ご自身の歯ぐきの状態を見直すきっかけにしてください。
歯ぐきからの出血は体からの危険信号(サイン)
歯磨きをしている時に歯ぐきから血が出ると、「いつものことだから大丈夫」と軽く考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、健康な状態の歯ぐきは、歯磨き程度の刺激で出血することはありません。歯ぐきからの出血は、お口の中に何らかのトラブルが発生していることを知らせる、体からの大切なサインなのです。このサインを見過ごさず、ご自身の口腔内の状態に目を向けることが、将来の歯の健康を守る第一歩となります。
「歯磨きのときだけ」と軽く考えず、原因を知ることが大切
歯ぐきからの出血を「歯磨きの時だけ」と軽く捉え、放置してしまうと、口腔内の問題がさらに進行し、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。一時的な症状だと思われがちですが、その背景には歯肉炎や歯周病といった深刻な病気が隠れていることも少なくありません。出血の原因を正しく理解し、適切な対処を行うことは、お口の健康を維持するために非常に重要です。このセクションでは、出血の裏に潜むさまざまな原因について詳しく解説し、ご自身の状況を把握する手助けをします。
歯ぐきから出血する主な原因
歯ぐきからの出血は、その原因が一つだけではないことをご存知でしょうか。お口の中の問題から、全身の健康状態に至るまで、さまざまな要因が複雑に絡み合って出血を引き起こすことがあります。このセクションでは、ご自身の状況と照らし合わせながら、これから詳しく見ていく主な原因、つまり歯肉炎や歯周病、誤った歯磨きの仕方、そして全身の疾患などがどのように出血に繋がるのかを全体的にご紹介します。
ほとんどのケースは歯肉炎・歯周病のサイン
歯ぐきからの出血の原因として、最も身近で多くの方に当てはまるのが「歯肉炎」や「歯周病」です。日本の成人のおよそ8割以上の方が、歯肉炎や歯周病に罹患していると言われています。これは、歯と歯ぐきの境目などに付着する「歯垢(プラーク)」の中に潜む細菌が、歯ぐきに炎症を引き起こし、その結果として出血を招くメカニズムによるものです。プラークは食べ物の残りカスと細菌の塊で、歯ブラシが届きにくい場所に溜まりやすく、これが歯ぐきの炎症の主な原因となります。
歯肉炎と歯周病の違いとは?
歯ぐきからの出血と一口に言っても、「歯肉炎」と「歯周病」ではその進行度合いが異なります。歯肉炎は、歯周病の「初期段階」と位置づけられます。これは歯ぐきだけが炎症を起こしている状態で、歯を支える骨(歯槽骨)にはまだ影響が及んでいません。歯ぐきが赤く腫れて、歯磨きなどによって出血しやすくなるのが特徴です。この段階であれば、適切な歯磨きや歯科医院でのクリーニングによって健康な状態に戻せる可能性が高いでしょう。
一方、歯周病は歯肉炎がさらに進行した状態を指します。炎症が歯ぐきだけでなく、歯を支える骨などの組織にまで広がり、これらの組織が破壊され始める、より深刻な病気です。歯ぐきが下がる、歯がぐらつく、口臭が強くなるなどの症状が現れ始めます。歯肉炎と歯周病は症状が似ている部分もありますが、炎症が歯を支える骨にまで及んでいるかどうかが大きな違いとなります。
歯周病が進行すると歯を失うリスクも
歯周病を放置し、進行させてしまうと、最終的には歯を失うという深刻な結果につながる可能性があります。実際、歯周病は日本の成人が歯を失う原因の第一位とされています。歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨という骨が少しずつ溶かされていきます。骨が溶けてしまうと、歯は徐々に支えを失い、ぐらつき始めます。初期の段階では自覚症状が少ないこともありますが、進行すると歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、さらに多くの細菌が溜まりやすくなります。
やがて、歯槽骨の破壊がさらに進むと、歯のぐらつきが大きくなり、食事をするのも困難になることがあります。そして最終的には、歯が自然に抜け落ちてしまったり、歯科医師による抜歯が必要になったりするケースも少なくありません。ご自身の歯を長く使い続けるためにも、歯周病の早期発見と適切な対策が非常に重要です。
間違った歯磨きによる刺激
歯ぐきからの出血は、歯肉炎や歯周病といった細菌が原因の炎症だけでなく、日々の歯磨きの仕方が原因で起こることもあります。良かれと思って丁寧に磨いているつもりでも、歯磨きの方法が適切でなければ、かえって歯ぐきに負担をかけてしまい、出血につながることがあるのです。
力の入れすぎで歯ぐきを傷つけている可能性
歯磨きの際に「ゴシゴシ」と強い力で磨く習慣がある方は、歯ぐきを傷つけて出血させてしまっている可能性があります。歯周病による出血は歯ぐきの炎症が原因ですが、強い力で歯を磨くことによる出血は、物理的に歯ぐきが傷つくことで起こります。この場合、歯ぐきに赤みや腫れがないにも関わらず、歯磨きのたびに出血するという特徴があります。
歯ブラシの毛先がすぐに開いてしまったり、磨いた後に歯ぐきにヒリヒリとした痛みを感じたりする場合は、力が強すぎるサインかもしれません。健康な歯ぐきは非常にデリケートなので、適切な力加減で優しく磨くことが大切です。
その他の原因:全身の健康状態や生活習慣
歯ぐきからの出血は、お口の中だけの問題に留まらず、私たちの全身の健康状態や日々の生活習慣が影響しているケースもあります。ホルモンバランスの変化や服用している薬、さらには糖尿病などの全身の病気が、歯ぐきの状態と密接に関わっていることがあるのです。このセクションでは、そういった口腔外の原因について解説し、お口の健康が全身とどのように関連しているのかをご紹介します。
ホルモンバランスの変化(妊娠中など)
特に女性の場合、ホルモンバランスの変化が歯ぐきの健康に影響を与えることがあります。代表的な例が「妊娠性歯肉炎」です。妊娠中は女性ホルモンの分泌量が増加し、これにより歯周病の原因となる細菌が活発になりやすくなります。また、歯ぐきの血管が拡張してうっ血しやすくなるため、歯ぐきが腫れたり、歯磨き時に出血しやすくなったりすることがあります。妊娠期間だけでなく、思春期や生理期間中、更年期など、ホルモンバランスが変動しやすい時期には、歯ぐきの炎症や出血が起こりやすくなる傾向があります。
これらの時期は、通常よりも一層丁寧な口腔ケアが求められます。ホルモンバランスの変化による影響を理解し、適切なケアを心がけることが、歯ぐきの健康維持につながります。
服用している薬の影響
現在服用しているお薬が、歯ぐきからの出血に影響を及ぼしている可能性も考えられます。特に、血液をサラサラにする作用のある「抗凝固剤」や「抗血小板剤」などを服用されている方は、わずかな刺激でも歯ぐきから出血しやすくなったり、一度出血すると血が止まりにくくなったりすることがあります。他にも、高血圧治療薬の一部や免疫抑制剤などが、歯ぐきの腫れや出血を招くケースも報告されています。
もしお薬を服用されていて、歯ぐきからの出血が気になる場合は、自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりすることは絶対に避けてください。必ずかかりつけの医師や歯科医師に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。お薬手帳を持参して、現在服用しているすべての薬について伝えることが大切です。
糖尿病などの全身疾患
歯ぐきの出血や歯周病は、お口の中の問題だけでなく、糖尿病などの全身の病気と深く関わっていることがあります。特に糖尿病の患者さんは、血糖値が高い状態が続くことで免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。歯周病も細菌感染症の一つであるため、糖尿病患者さんは歯周病を発症しやすく、また進行もしやすい傾向があるのです。さらに、血流が悪くなることも歯ぐきの健康に悪影響を及ぼします。
興味深いことに、この関係性は一方通行ではありません。重度の歯周病は、炎症によって全身に影響を及ぼし、糖尿病のコントロールを悪化させる可能性も指摘されています。このように、お口の健康と全身の健康は密接に連携しているため、歯ぐきの出血を放置せず、全身の健康管理の一環として捉えることが非常に重要です。
今日から始められる!自宅でできる歯ぐきの出血対策
歯ぐきからの出血は、多くの方が経験する口腔内のトラブルですが、「どうしたら良いのかわからない」と感じる方も少なくありません。これまでのセクションで出血の危険性や原因についてご理解いただけたと思いますが、このセクションでは、ご自宅で今日からすぐに実践できる具体的なセルフケアの方法をご紹介します。日々の少しの工夫と正しい知識で、健康な歯ぐきを取り戻し、維持することは十分に可能です。ご自身のペースで無理なく取り組める方法ばかりですので、ぜひ前向きに読み進めてください。
正しい歯磨きの方法を見直す
毎日の歯磨きは、口腔ケアの基本中の基本ですが、多くの方が自己流になってしまいがちです。実は、歯ブラシの選び方や磨き方が間違っていると、かえって歯ぐきを傷つけたり、プラークを十分に除去できなかったりして、出血の原因になることがあります。このセクションでは、単に「磨く」だけでなく、「どのように磨くか」に焦点を当て、出血の改善に繋がる正しい歯磨きの方法を詳しく解説します。ご自身の歯磨きの習慣を見直すきっかけにしていただければ幸いです。
歯ブラシは「柔らかめ」を選び、優しく磨く
歯ぐきから出血している場合、歯ぐきは非常にデリケートな状態です。このような時は、毛先が硬い歯ブラシや、強い力でゴシゴシ磨くことは避けてください。歯ぐきをさらに傷つけ、出血を悪化させてしまう可能性があります。歯ブラシを選ぶ際には、毛先が「柔らかめ」のものを選びましょう。柔らかい毛先の歯ブラシは、歯ぐきに優しく、炎症を起こした部分を刺激しすぎずにプラークを除去できます。
磨く際の力加減も重要です。目安としては、歯ブラシを鉛筆を持つように軽く握り、歯ぐきを優しくマッサージするような感覚で磨いてください。歯ブラシの毛先が広がりすぎない程度の力で十分です。もし、歯ブラシの毛先がすぐに開いてしまう場合は、力が強すぎるサインかもしれません。優しい力でも、適切な方法で磨けばプラークは十分に除去できますので、焦らず丁寧に行うことが大切です。
歯と歯ぐきの境目を意識した磨き方(バス法など)
歯周病の主な原因となるプラークは、歯と歯ぐきの境目にある「歯周ポケット」と呼ばれる溝に溜まりやすい性質があります。この部分のプラークを効果的に除去するために推奨されるのが、「バス法」と呼ばれる歯磨き方法です。
バス法では、歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当てます。そして、その場で小刻みに優しく振動させるように磨きます。この時、歯ブラシの毛先が歯周ポケットの中に少し入り込むイメージを持つと良いでしょう。一本一本の歯に対して丁寧に、軽い力で細かく動かすことがポイントです。この磨き方を行うことで、歯周ポケット内のプラークを効率良くかき出し、歯肉の炎症を抑えることに繋がります。
最初は難しいと感じるかもしれませんが、鏡を見ながら練習することで、徐々に正しい磨き方を身につけることができます。炎症が起きている部分は出血しやすいですが、恐れずに継続して優しく磨き続けることで、通常2〜3日程度で歯ぐきの状態が改善し、出血も減っていくことが多いです。
歯間ケアでプラーク(歯垢)の除去率をアップ
毎日しっかり歯磨きをしているつもりでも、実は歯ブラシだけではすべてのプラークを除去することはできません。特に、歯と歯の間の狭い隙間や、歯並びが複雑な部分は、歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが最も残りやすい「磨き残しゾーン」となりがちです。このような場所に溜まったプラークは、時間とともに歯石へと変化し、歯肉炎や歯周病を進行させる大きな原因となります。
実際、歯ブラシ単独でのプラーク除去率は約60%程度と言われています。しかし、歯ブラシに加えてデンタルフロスや歯間ブラシといった「歯間ケア用品」を併用することで、プラーク除去率は80%から90%近くまで大幅に向上させることが可能です。歯と歯の間に残ったプラークは、出血の原因となる歯周病原細菌の温床となりますので、毎日の歯磨きに歯間ケアを取り入れることは、健康な歯ぐきを保つ上で非常に重要です。
デンタルフロスや歯間ブラシを毎日の習慣に
歯間のプラークを除去するための効果的なツールとして、デンタルフロスと歯間ブラシがあります。どちらを選ぶかは、ご自身の歯と歯の間の隙間の広さによって使い分けるのが一般的です。隙間が狭い場所や、特に前歯の密着した部分にはデンタルフロスが適しています。フロスを約40cmにカットし、両手の中指に巻きつけ、人差し指と親指で操作しながら、歯の側面に沿わせて優しく挿入し、上下に動かしてプラークを絡め取ります。
一方、歯と歯の間に比較的広い隙間がある奥歯や、歯周病で歯ぐきが下がって隙間ができた場所には、歯間ブラシが効果的です。歯間ブラシは、さまざまなサイズがありますので、ご自身の歯間に合ったサイズを選ぶことが大切です。無理に大きいサイズを挿入すると歯ぐきを傷つける原因になりますので、最初は細めのものから試してみるか、歯科医院で相談して適切なサイズを選んでもらいましょう。歯間ブラシも、歯ぐきを傷つけないように、ゆっくりと挿入し、前後に数回動かして汚れを除去します。
歯間ケアを始めたばかりの頃は、出血があるかもしれませんが、これは炎症を起こした歯ぐきから一時的に血が出ているだけで、継続してケアを行うことで炎症が治まり、数日後には出血も改善してくることが多いです。毎日の習慣として取り入れ、健康な歯ぐきを目指しましょう。
生活習慣の改善で歯周病リスクを低減
歯ぐきの出血や歯周病は、口腔内のケアだけでなく、全身の健康状態や日々の生活習慣とも深く関わっています。例えば、栄養バランスの偏った食事、睡眠不足、過度なストレスなどは、免疫力を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱めてしまう可能性があります。バランスの取れた食事を心がけ、十分な睡眠時間を確保し、適度な運動を取り入れることで、全身の免疫力を高め、結果として歯ぐきの健康維持にも繋がります。
特に、喫煙は歯周病の最大のリスク因子の一つとして知られています。タバコに含まれる有害物質は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫細胞の働きを阻害するため、歯周病の発症や進行を早めるだけでなく、治療の効果も低下させてしまいます。もし喫煙習慣がある場合は、禁煙を検討することが、歯ぐきの健康を守る上で非常に有効な一歩となります。
また、ストレスも歯ぐきの健康に影響を与えることがあります。ストレスを感じると、無意識のうちに歯を食いしばったり、歯ぎしりをしたりすることがあり、これが歯や歯ぐきに過度な負担をかける原因となることがあります。趣味やリラクゼーションを取り入れるなどして、日頃からストレスを上手に管理することも、口腔内の健康維持には欠かせない要素です。
セルフケアで改善しない・悪化する場合は歯科医院へ
自宅での丁寧なケアを続けても歯ぐきからの出血が改善しない場合や、出血以外にも気になる症状が現れた場合には、自己判断で放置せずに、速やかに歯科医院を受診することが大切です。出血が続くということは、セルフケアだけでは対応しきれない問題が口腔内に潜んでいるサインかもしれません。専門家である歯科医師や歯科衛生士に相談し、適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、より早期に健康な状態を取り戻すことができます。
このセクションでは、どのような症状が見られたら歯科医院を受診すべきか、また歯科医院でどのような検査や治療が行われるのかについて、具体的な情報をご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、適切な行動を判断する際の参考にしてください。
受診を検討すべき症状のチェックリスト
ご自身の歯ぐきの出血が、セルフケアで対応できる範囲を超えているかどうかを判断するために、以下のチェックリストを活用してください。もし一つでも当てはまる項目がある場合は、早期の歯科医院への相談を検討しましょう。
2〜3日ケアを続けても出血が止まらない
適切な歯磨き方法を実践し、デンタルフロスや歯間ブラシを使った丁寧なセルフケアを2〜3日(長くとも1週間程度)続けているにもかかわらず、歯ぐきからの出血が一向に改善しない場合は、歯科医院への受診を検討する目安となります。健康な歯ぐきであれば、正しいケアによってプラークが除去されることで、比較的短期間で炎症が治まり、出血も収まることがほとんどです。
しかし、セルフケアだけでは取り除けないほど硬く付着した歯石がある場合や、歯周病が進行して歯周ポケットの奥深くに細菌が入り込んでいる場合は、ご自宅でのケアだけでは症状を改善することが難しいです。このような状況では、歯科医院での専門的なクリーニングや治療が必要となります。放置すると歯周病がさらに悪化するリスクがあるため、早めに専門家のアドバイスを求めることが大切です。
歯ぐきに強い腫れや痛みがある
単に歯ぐきから血が出るだけでなく、歯ぐきが赤く腫れ上がっていたり、触れると明らかにブヨブヨと膨らんでいたり、さらにはズキズキとした強い痛みを伴う場合は、早急に歯科医院を受診してください。これは、歯ぐきに急性炎症が起きているか、内部に膿が溜まっている可能性が高い危険なサインです。
特に、歯ぐきが熱を持っているように感じたり、歯ぐきの奥に硬いしこりのようなものを感じたりする場合、あるいは何もしていなくても持続的に痛みが続く場合は、放置すると感染が広がり、より深刻な状態に発展する恐れがあります。我慢せずに、すぐに専門家の診察を受けましょう。
複数の場所から出血する
歯ぐきからの出血が、特定の1箇所だけでなく、歯磨きをするたびに口の中の複数の場所で起こる場合も注意が必要です。これは、局所的な問題というよりも、お口全体の広範囲で歯肉炎や歯周病が進行している可能性が高いことを示しています。
また、全身の健康状態が悪化している兆候として、複数箇所から出血が見られるケースも稀にあります。例えば、血液の病気や特定の薬剤の副作用などが原因で、歯ぐき全体がデリケートになり、出血しやすくなっていることも考えられます。そのため、広範囲での出血が続く場合は、自己判断せずに歯科医院を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
歯科医院で行われる検査と治療
歯科医院を受診することに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、何が行われるのかを事前に知ることで、安心して一歩を踏み出すことができます。歯ぐきからの出血を訴えて歯科医院を訪れた際には、主に以下のような検査や治療が行われます。
歯周ポケットの深さのチェック
歯科医院での最初の検査の一つに、歯周ポケットの深さの測定があります。これは「プローブ」と呼ばれる細い器具を使い、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)の深さを測るものです。健康な歯ぐきでは深さが1〜3mm程度ですが、歯周病が進行すると4mm以上と深くなり、このポケットの奥に歯周病菌が溜まりやすくなります。
この検査は、歯周病の進行度を客観的に診断するために非常に重要です。測定時にチクッとした軽い刺激を感じることはありますが、痛みはほとんどありませんのでご安心ください。出血の有無やプローブが届く範囲などを確認することで、現在の歯周病の状態を正確に把握することができます。
歯垢・歯石の除去(クリーニング)
歯ぐきからの出血の主な原因であるプラークや歯石を除去することは、歯科治療の基本です。ご自宅での歯磨きでは取り除くことが難しい、硬く石灰化した「歯石」や、細菌が集合して形成された「バイオフィルム」は、歯科医師や歯科衛生士が専用の器具(スケーラーなど)を使って徹底的に除去します。
この処置を「スケーリング」と呼び、歯周病治療の第一歩となります。歯石は歯ブラシでは落とすことができないため、歯石が付着している場合は、必ず専門家によるクリーニングが必要です。歯石がなくなることで、歯ぐきの炎症が治まり、出血も改善に向かうことが期待できます。
進行度に応じた歯周病治療
歯周病の進行度合いに応じて、クリーニングだけでは不十分な場合に、さらに専門的な治療が行われることがあります。例えば、歯周ポケットが深く、歯石が歯ぐきの奥深くに入り込んでいる場合には、「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)」という処置が行われます。
これは、歯周ポケットの奥深くにある歯石や感染した歯根の表面をきれいに清掃し、滑らかにすることで、歯周病菌の再付着を防ぎ、歯ぐきの回復を促す治療です。さらに、歯周病が非常に進行してしまっている場合には、歯周外科手術や、失われた歯周組織を再生させる「歯周組織再生誘導法」といった、より高度な治療が検討されることもあります。歯科医師が患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な治療計画を提案しますので、ご自身の症状や不安な点があれば遠慮なく相談してください。
出血しない健康な歯ぐきを保つための予防習慣
歯ぐきからの出血が改善し、健康な状態を取り戻せたなら、その良い状態をいかに維持していくかが重要になります。一度良くなったからといって、ケアを怠ってしまうと、再び出血が始まってしまうかもしれません。ここでは、健康な歯ぐきを長期間保つために、日常的に心がけていただきたい予防習慣についてお話しします。
毎日の丁寧なセルフケアの継続
健康な歯ぐきを維持するための最も基本的な予防習慣は、何よりも「毎日の丁寧なセルフケアを継続すること」です。歯磨きや歯間ケアは、治療が終わったからといってやめてしまうものではありません。これらは、お口の健康を守り続けるために生涯にわたって実践していくべき大切な習慣です。
日々のセルフケアを地道に続けることで、歯垢(プラーク)の蓄積を防ぎ、歯ぐきの炎症を未然に防ぐことができます。一見、単純な毎日の習慣に思えるかもしれませんが、この継続的な努力こそが、将来の歯の健康、そして全身の健康を大きく左右することになります。正しい歯磨きの方法とデンタルフロスや歯間ブラシを使った歯間ケアを、ぜひ日々の生活の一部として取り入れてください。
定期的な歯科検診でプロのチェックを受ける重要性
ご自身で行うセルフケアは非常に大切ですが、それだけではどうしても限界があります。歯ブラシでは届きにくい場所や、ご自身では気づきにくい歯石の蓄積など、セルフケアだけではカバーしきれない部分があるためです。また、歯周病は自覚症状がないまま進行することも多く、気づいた時にはかなり悪化しているというケースも少なくありません。
そこで重要になるのが、「定期的な歯科検診とプロフェッショナルクリーニング」です。歯科医院では、ご自身のケアでは落としきれない歯石やバイオフィルムを専用の機器で徹底的に除去し、お口の中を清潔な状態に保ちます。さらに、歯科医師や歯科衛生士が、歯ぐきの状態や歯周病の進行具合を専門的な視点でチェックし、問題があれば早期に発見して適切なアドバイスや治療を行うことができます。定期的なプロのチェックを受けることで、問題を未然に防ぎ、もし問題が見つかっても早期に対応することで、大切な歯を長持ちさせることに繋がります。半年に一度など、ご自身のライフスタイルに合わせた頻度で、ぜひ定期検診を受診してください。
まとめ:歯ぐきの出血は放置せず、早めの対策で健康な口内環境を守ろう
歯ぐきからの出血は、決して軽視してはいけない体からの重要なサインです。健康な歯ぐきは通常、歯磨き程度の刺激では出血しません。もし歯磨き時に出血するようであれば、それは歯肉炎や歯周病といった口腔内の問題、あるいは全身の健康状態の変化を示している可能性が高いです。
この記事では、歯ぐきの出血の主な原因から、ご自宅で実践できるセルフケアの方法、そして歯科医院を受診すべき症状や治療内容までを詳しくご説明しました。原因の多くは歯周病菌による炎症であり、正しい歯磨きや歯間ケアを継続することで、多くの場合改善が見られます。柔らかめの歯ブラシで優しく磨くこと、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間のプラークを除去することが非常に大切です。
しかし、ご自宅でのセルフケアを2~3日続けても出血が止まらない場合や、歯ぐきの強い腫れ、痛み、複数の場所からの出血が見られる場合は、迷わず歯科医院を受診してください。自己判断で放置すると、歯周病が進行し、最終的には大切な歯を失うリスクにもつながりかねません。
一度健康を取り戻した歯ぐきを維持するためには、毎日の丁寧なセルフケアと、定期的な歯科検診が不可欠です。プロによるクリーニングとチェックは、ご自身では気づけない問題の早期発見・早期対応に繋がり、健康な口内環境を長く保つための最良の方法です。歯ぐきの出血を見過ごさず、早めの対策で、健康な毎日を守っていきましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
高橋 衛 | Takahashi mamoru
岩手医科大学歯学部卒業後、岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座入局し、
医療法人 高橋衛歯科医院設立 理事長就任、MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS 開設
【所属】
・日本歯科医師会
・岩手県歯科医師会
・盛岡市歯科医師会
・歯科医師臨床研修指導歯科医
・岩手県保険医協会
・日本口腔外科学会
・日本口腔インプラント学会
・EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION
・AMERICAN ACADEMY PERIODONTOLOGY
・岩手医科大学歯学会
・デンタルコンセプト21 会員
・日本歯科東洋医学会
・JIADS Club 会員
・P.G.I Club 会員
・スピード矯正研究会 会員
・床矯正研究会 会員
・近代口腔科学研究会 会員
【略歴】
・岩手医科大学歯学部 卒業
・岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座 入局
・「高橋衛歯科医院」 開業
・「MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS」 開業
岩手県盛岡市の歯医者・歯科
『高橋衛歯科医院』
住所:岩手県盛岡市北天昌寺町7−10
TEL:019-645-6969