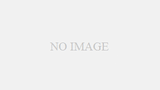お子さまの歯の健康は、成長と発達にとって非常に大切です。初めての歯が生え始めたとき、多くの親御さんが「いつから歯磨きを始めればいいの?」「正しい磨き方がわからない」「うちの子は歯磨きを嫌がって困る」といったお悩みを抱えていらっしゃいます。ご安心ください、この記事では、そうした疑問や不安を解消し、お子さまの歯を虫歯から守るための具体的な方法を詳しくご紹介します。
乳歯は、ただ生え変わる一時的なものではなく、永久歯の成長や顎の発達、さらには食事や発音にも深く関わる重要な役割を担っています。この記事を最後までお読みいただくことで、お子さまの年齢に合わせた適切な歯磨きのタイミングや方法、そして歯磨きを嫌がるお子さまへの効果的な対処法まで、実践的な知識を身につけることができるでしょう。今日から、お子さまの健やかな笑顔を守るための歯磨き習慣を、自信を持って始めましょう。
なぜ子供の歯磨きは重要?乳歯が担う役割
「いずれ生え変わるから」と、乳歯のケアを軽視していませんか。実は、乳歯は単なる一時的な歯ではありません。子供の成長において、永久歯の健康や顎の発達、さらには全身の健康にまで影響を及ぼす、非常に重要な役割を担っています。このセクションでは、乳歯が持つかけがえのない機能と、それが将来の健康にどう繋がるのかを具体的に見ていきましょう。
乳歯が将来の永久歯や顎の発達に与える影響
乳歯には、将来生えてくる永久歯のために「場所取り」をするという大切な役割があります。乳歯は、それぞれの永久歯が正しい位置に生えるためのガイド役となり、スペースを確保しています。もし虫歯などで乳歯を早くに失ってしまうと、そのスペースが狭くなり、永久歯が重なって生えてきたり、デコボコの歯並びになったりするリスクが高まります。このような歯並びの乱れは、見た目だけでなく、噛み合わせの悪さや清掃性の低下にも繋がります。
また、乳歯は顎の骨の正常な発育を促す上でも不可欠です。子供が食べ物をしっかりと噛むことで、顎の骨に適度な刺激が加わり、健全な成長が促されます。この刺激によって、顎の骨が十分な大きさに育ち、永久歯がきれいに並ぶための土台が作られます。乳歯がきちんと機能しないと、顎の成長が不十分になり、永久歯の並ぶスペースが足りなくなる可能性も考えられます。
子供の虫歯が引き起こすリスク
乳歯の虫歯は、単に歯が痛むだけでなく、子供の健康と成長に様々な悪影響を及ぼします。虫歯が進行すると、食べ物を噛むのが困難になり、食欲不振や偏食の原因となることがあります。その結果、必要な栄養が十分に摂取できず、身体の成長に影響を及ぼす可能性も考えられます。また、前歯に大きな虫歯があると、言葉を発する際の発音にも支障をきたすことがあります。
さらに、乳歯の虫歯は、後から生えてくる永久歯にも悪影響を与えるリスクがあります。乳歯の虫歯菌が口の中に多く存在すると、新しく生えてきたばかりの永久歯にも感染しやすくなり、永久歯も虫歯になりやすくなってしまいます。また、乳歯の根の先に炎症が起きると、その下にある永久歯の芽(歯胚)に影響を与え、永久歯のエナメル質形成不全などの異常を引き起こすこともあります。
このように、乳歯の虫歯を放置することは、子供の食事、発音、そして将来の永久歯の健康にも連鎖的な悪影響を及ぼす可能性があるため、親御さんは乳歯の虫歯予防の重要性を深く認識し、早期からの適切なケアを心がけることが大切です。
子供の歯磨きはいつから始める?年齢別のケア方法
子供の歯のケアは、お子様の成長段階や歯の生え方に合わせて、適切な方法で行うことが大切です。画一的なケアではなく、お子様の年齢に合ったアプローチをすることで、効果的に虫歯を予防し、歯磨きを楽しい習慣へと導くことができます。このセクションでは、歯が生え始める前から乳歯が生えそろうまでの期間をいくつかのステップに分け、それぞれの時期でどのようなケアをすべきかを具体的に解説します。ご自身のお子様の年齢に合わせた最適な歯磨きケアを見つけるためのガイドとしてご活用ください。
【0歳】歯が生える前:ガーゼでの口腔ケア
歯が生え始める前の0歳の時期は、まだ歯を磨く必要はありませんが、口の中に触れられることに慣れさせるための大切な準備期間です。この口腔ケアの主な目的は、将来の歯磨きへのスムーズな移行を促すことにあります。口の中を触られることに抵抗感をなくし、清潔にする習慣の第一歩として取り組みましょう。
具体的な方法としては、保護者の方がきれいに手を洗い、清潔なガーゼを指に巻きつけます。授乳後やお風呂上がりなど、お子様がリラックスしているタイミングで、ガーゼで歯茎や舌を優しく拭ってあげてください。強くこする必要はなく、なでるように触れるだけで十分です。このケアを毎日続けることで、お子様は口の中に何か入ることへの抵抗感が薄れ、歯ブラシを受け入れやすくなります。
【6ヶ月頃〜】乳歯の生え始め:歯ブラシに慣れる
最初の乳歯が生え始める生後6ヶ月頃からは、いよいよ歯ブラシデビューの準備期間です。この段階のケアの目標は、歯をきれいに磨き上げることよりも、お子様が歯ブラシの感触に慣れ、歯磨きタイムを楽しい時間と認識することにあります。無理強いせず、遊びの一環として取り入れるのがポイントです。
まずは、赤ちゃん用のやわらかいシリコン製歯ブラシやヘッドの小さい歯ブラシを用意しましょう。保護者の方が楽しそうに歯ブラシをお子様に見せながら、「カミカミする?」などと声かけをしてみてください。そして、優しく歯ブラシを口に入れて、生え始めた歯や歯茎に軽く触れてみましょう。嫌がる場合はすぐにやめ、機嫌の良い時に再度試すなど、焦らずゆっくりと慣れさせていくことが大切です。
【1歳半頃〜】奥歯の萌出期:仕上げ磨きの開始
1歳半頃になると、乳歯の奥歯が生え始めます。この時期から「仕上げ磨き」が非常に重要になります。なぜなら、奥歯は溝が深く、食べかすが詰まりやすい構造をしており、お子様自身の歯磨きだけでは汚れを十分に落としきることが難しいからです。
奥歯の虫歯は進行が早く、痛みが出やすい特徴があります。保護者の方がお子様の磨き残しをしっかりとチェックし、きれいに磨き上げてあげる「仕上げ磨き」を行うことで、効果的に虫歯を予防することができます。この時期から仕上げ磨きを習慣化することは、お子様の将来の歯の健康を守る上で欠かせないステップとなります。
お子様が自分で磨く歯磨きと、保護者の方が行う仕上げ磨きの両方を組み合わせることで、お子様の歯はよりきれいに保たれます。仕上げ磨きは、お子様が自分で歯磨きができるようになるまで、毎日続けるように心がけましょう。
【3歳頃〜】乳歯列の完成期:歯磨きの習慣化
3歳頃になると、多くのお子様で乳歯がすべて生えそろい、乳歯列が完成します。この時期のケアの最大のポイントは、「歯磨きの習慣化」に焦点を当てることです。食後や寝る前など、決まった時間に歯磨きをするという生活リズムを確立することが、虫歯予防にとって非常に重要になります。
お子様には自分で歯を磨く楽しさや意欲を持たせつつ、必ず保護者の方が仕上げ磨きで磨き残しがないかを確認し、きれいに磨き上げてあげましょう。この自立とサポートのバランスが大切です。自分で磨く練習をしながら、まだ届かない部分や磨きにくい部分は保護者の方が丁寧にケアすることで、お子様の歯は健康に保たれます。
歯磨きを習慣化するためには、「歯磨きは楽しいもの」と感じさせることが重要です。歌を歌ったり、絵本を読み聞かせたりしながら、毎日の一連のルーティンとして定着させていきましょう。規則正しい歯磨き習慣は、お子様の生涯にわたる歯の健康の基礎となります。
【実践】子供の正しい歯磨きの方法と仕上げ磨きのコツ
これまでのセクションでは、お子様の歯の健康がなぜ大切なのか、そして成長の段階ごとにどのようなケアが必要かについてお話ししてきました。ここでは、その知識を実践に活かすための具体的な歯磨きの方法を詳しくご紹介します。
歯ブラシや歯磨き粉といった道具の選び方から、実際にどのように歯を磨き、仕上げ磨きをするのかまで、ご家庭ですぐに実践できる具体的な情報が満載です。お子様が毎日楽しく歯磨きできるようなヒントも交えながら、親御さんが自信を持って歯のケアに取り組めるよう、分かりやすく解説していきます。
準備するもの:歯ブラシと歯磨き粉の選び方
お子様の歯磨きを始めるにあたって、最初に準備する大切なアイテムが歯ブラシと歯磨き粉です。これらの選び方は、お子様が歯磨きを嫌がらずに続けられるか、そして効果的に虫歯を予防できるかに大きく影響します。
このセクションでは、お子様の成長段階に合わせた最適な歯ブラシの選び方と、虫歯予防に効果的なフッ素配合歯磨き粉の適切な選び方と使い方について、詳しく見ていきましょう。
子供の年齢に合わせた歯ブラシの選び方
お子様の歯ブラシを選ぶ際は、年齢や口の中の発達段階に合わせることがとても重要です。適切な歯ブラシを選ぶことで、安全かつ効果的に歯磨きができ、お子様も快適に感じやすくなります。
まず、乳歯が生え始める0歳から2歳頃のお子様には、ヘッドが小さく、毛が非常に柔らかいタイプの歯ブラシを選びましょう。喉の奥まで入らないように、安全ストッパーがついているものや、保護者の方が持ちやすい長い柄のものがおすすめです。この時期は「歯ブラシに慣れる」ことが目的なので、お子様が自分で持って遊べるようなシリコン製の歯ブラシも活用できます。
次に、乳歯が揃ってくる3歳から5歳頃のお子様には、引き続きヘッドの小さいものを選びますが、少しずつ自分で磨く練習を始めるため、お子様自身が握りやすい太めの柄の歯ブラシが良いでしょう。毛の硬さは「やわらかめ」が基本です。保護者の方が行う仕上げ磨き用には、さらにヘッドが小さく、細かく動かしやすい歯ブラシを選ぶと、奥歯の裏側や歯と歯の間など、磨きにくい場所にもしっかりと届きます。
フッ素配合歯磨き粉の適切な使用量と選び方
フッ素は歯質を強くし、虫歯菌の活動を抑える効果があるため、お子様の虫歯予防にはフッ素配合歯磨き粉の活用が推奨されます。しかし、年齢に応じた適切な量を使用することが大切です。
例えば、3歳未満のお子様には、歯磨き粉の量は米粒程度(1〜2mm)で十分です。3歳から5歳のお子様には、グリーンピース大(5mm程度)の量を目安にしましょう。これらの量は、万が一飲み込んでしまっても安全とされる範囲内です。歯磨き粉を選ぶ際には、フッ素濃度が表示されているか確認し、お子様の年齢に合った濃度(低年齢向けには低濃度のもの)を選ぶようにしてください。
また、歯磨き粉を使用した後、うがいを大量の水で何度もしてしまうと、フッ素が洗い流されてしまい、効果が薄れてしまいます。フッ素を口の中に留めて効果を発揮させるためには、うがいは少量の水で1回程度に留めるのがポイントです。お子様が歯磨きを嫌がらないように、味や香りがお子様の好みに合うものを選ぶのも良い方法ですが、キシリトール配合など、虫歯になりにくい甘味料が使われているものを選びましょう。
基本的な歯の磨き方と姿勢
適切な歯ブラシと歯磨き粉を選んだら、次に大切なのは「どのように磨くか」そして「どのような姿勢で磨くか」という点です。効果的な歯磨きは、単に歯ブラシを動かすだけでなく、お子様が快適に感じ、磨き残しなく汚れを落とすための工夫が求められます。
ここでは、保護者の方がお子様を磨きやすい「寝かせ磨き」の具体的なポイントと、歯の部位ごとに適した磨き方、そして注意すべき点について詳しく解説していきます。
保護者が行いやすい「寝かせ磨き」のポイント
小さなお子様の歯磨きには、「寝かせ磨き」という姿勢が多くの歯科専門家から推奨されています。これは、保護者の方の膝の上にお子様の頭を乗せ、仰向けに近い状態で歯磨きを行う方法です。
この姿勢をとることで、お子様は体が安定し、保護者の方は口の中全体をしっかりと見渡せるようになります。特に奥歯の裏側や歯と歯の間など、見えにくい部分も確認しながら丁寧に磨けるため、磨き残しを大幅に減らすことができます。また、照明を当てることで口の中がさらに見やすくなり、より正確な歯磨きにつながります。
お子様がリラックスして寝かせ磨きを受け入れてくれるよう、最初は絵本を読み聞かせたり、優しい声で歌いかけたりしながら、楽しく行う工夫も大切です。無理強いせず、徐々に慣らしていくことで、お子様も安心して歯磨きの時間を過ごせるようになります。
部位別の磨き方と注意点
お子様の歯を磨く際は、それぞれの歯の部位に合わせた磨き方を知ることが重要です。特に汚れがたまりやすい部分を意識して磨くことで、効率的に虫歯を予防できます。
歯ブラシは「ペングリップ」という鉛筆を持つような持ち方で、優しく握るのが基本です。前歯の表側や裏側は、歯ブラシを縦にして小刻みに動かし、一本ずつ丁寧に磨きます。奥歯の噛み合わせの面は、溝が深く汚れがたまりやすいので、歯ブラシの毛先を溝にしっかり当てて、細かく振動させるように磨きましょう。また、歯と歯茎の境目は汚れがたまりやすいにもかかわらず、見落としがちです。歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で当て、軽い力で小刻みに動かして汚れをかき出すように磨いてください。
歯磨きをする際は、決して力を入れすぎないことが大切です。強い力で磨くと、歯茎を傷つけたり、エナメル質を削ってしまったりする原因になります。お子様の歯と歯茎はデリケートなので、優しく、しかし確実に汚れを落とすことを心がけましょう。磨き終わったら、仕上げにフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れも除去すると、さらに虫歯予防効果が高まります。
子供が歯磨きを嫌がる原因と対処法
多くの親御さんが経験される「子供の歯磨きイヤイヤ期」は、決して特別なことではありません。この時期は一時的なものであり、その原因を理解し、適切な方法で対処することで、乗り越えることができます。このセクションでは、なぜ子供が歯磨きを嫌がるのか、その具体的な理由と、ご家庭で実践できる効果的な対処法について詳しくご紹介します。お子さんが楽しく歯磨きできるようになるためのヒントがきっと見つかるはずです。
子供が歯磨きを嫌がる主な理由
子供が歯磨きを嫌がる理由は一つではなく、いくつかの心理的、身体的な要因が絡み合っていることがほとんどです。まず挙げられるのは、口の中に異物が入ることへの恐怖感や不快感です。特に小さなお子さんは、慣れない歯ブラシが口に入ることに警戒心を抱きやすく、それが嫌な感情につながることがあります。
また、歯ブラシが歯茎に当たって痛みを感じたり、保護者の力の入れ具合によっては不快感が生じたりすることもあります。特に、乳歯が生え始めの時期は歯茎が敏感なため、少しの刺激でも痛く感じやすいものです。さらに、眠くてぐずる時間帯に無理やり歯磨きをさせられたり、親御さんの真剣な表情が子供にとっては怖く感じられたりすることも、歯磨きを嫌がる原因となり得ます。
成長の過程で自我が芽生え、「イヤイヤ期」を迎えるお子さんにとって、「自分でやりたい」という気持ちと「親にやらされたくない」という気持ちが葛藤し、歯磨きがその対象となることも少なくありません。これらの原因を子供の視点から理解することで、親御さんも冷静に対応し、適切な対処法を見つける第一歩となるでしょう。
歯磨きを楽しい時間に変えるアイデア
歯磨きを「嫌な義務」と感じさせないためには、いかにして「楽しい時間」に変えるかが鍵となります。このセクションでは、お子さんの気持ちを前向きに切り替え、自ら歯磨きに取り組む意欲を引き出すための具体的なアプローチをご紹介します。ちょっとした工夫で、毎日の歯磨きタイムが親子のコミュニケーションの時間となり、歯磨き習慣の定着にも繋がるでしょう。
歌や絵本、アプリなどを活用する
歯磨きの時間を子供にとって魅力的なイベントに変えるには、歌や絵本、アプリといったツールが大いに役立ちます。例えば、「歯磨きの歌」を一緒に歌いながら磨くことで、歯磨きの時間を楽しく演出できますし、歌の長さで磨く時間の目安にもなります。歯磨きをテーマにした絵本を読み聞かせることも効果的です。絵本を通じて、歯磨きをすることの楽しさや大切さを自然と子供に伝えることができます。
スマートフォンやタブレットのアプリの中には、歯磨きを応援してくれるキャラクターが登場したり、ゲーム感覚で歯磨きができるものもあります。これらのツールは、子供の興味を引きつけ、歯磨きに対するネガティブな感情を払拭するのに役立ちます。ただし、画面に集中しすぎず、親御さんが隣で声をかけながら、あくまで補助的なツールとして活用することが大切です。
保護者も一緒に歯磨きをする
子供は、大人の行動をよく見ていて、それを真似したいという強い欲求を持っています。そのため、保護者の方が楽しそうに一緒に歯磨きをすることで、子供も歯磨きを「自分もやりたいこと」として自然に受け入れるようになります。これは、歯磨きの習慣化において非常に効果的な方法の一つです。
例えば、洗面所の鏡の前で親子並んで一緒に歯磨きをしたり、お互いの歯を「きれいになったね!」とチェックし合ったりすることで、歯磨きの時間が楽しいコミュニケーションの時間に変わります。保護者が「ママも頑張って歯磨きするから、〇〇ちゃんも頑張ろうね」などと声をかけることで、子供は安心感を持ち、自ら歯ブラシを持つようになるでしょう。
終わった後にたくさん褒めてあげる
歯磨きが終わった後の「ポジティブなフィードバック」は、子供のやる気を引き出し、次回の歯磨きへの意欲を高めるために非常に重要です。たとえその日の歯磨きが完璧にできなくても、少しでも協力して口を開けてくれたことや、歯ブラシを頑張ってくれたことなどを具体的に褒めてあげましょう。
「わぁ、〇〇ちゃんの歯、ピカピカになったね!」「バイキンさん、いなくなったかな?よく頑張ったね!」など、子供が喜びそうな言葉を選ぶと良いでしょう。親御さんの優しい言葉や笑顔は、子供にとって大きな達成感となり、自己肯定感を育むことにも繋がります。この褒める習慣を続けることで、歯磨きが「褒められる嬉しい時間」というポジティブな記憶として定着していきます。
歯磨き以外でできる虫歯予防
これまで、お子様の歯磨きの方法について詳しく見てきましたが、虫歯予防は歯磨きだけで完結するものではありません。毎日の歯磨きは虫歯予防の基本であり最も重要な「守り」のケアですが、さらに一歩進んだ「攻め」の予防策を組み合わせることで、より効果的にお子様の歯の健康を守ることができます。ここでは、日々の食生活で気をつけたいことや、歯科医院での専門的なケアの重要性について、総合的なアプローチでご紹介します。
食生活で気をつけること
虫歯の直接的な原因となるのが、お口の中の細菌が糖分をエサにして酸を作り出すことです。この酸が歯を溶かすことで虫歯は進行します。そのため、日々の食生活において糖分との付き合い方を工夫することが、虫歯予防には欠かせません。
ジュースやお菓子を完全に与えないようにするのは難しいですし、お子様にとってもストレスになることがあります。大切なのは「与え方」にメリハリをつけることです。例えば、おやつやジュースは時間を決めて与え、だらだらと長時間食べ続けたり飲んだりすることは避けるようにしましょう。食事と食事の間に何度も口の中に糖分が入ると、お口の中が酸性の状態が続き、歯が溶けやすい環境になってしまいます。食事やおやつの後は、水やお茶を飲んで口の中をすすぐ習慣をつけるだけでも、虫歯菌の活動を抑える効果が期待できます。
また、よく噛んで食べられるような食材を取り入れることも大切です。噛むことで唾液の分泌が促され、唾液の持つ虫歯菌を洗い流す作用や、酸を中和する作用が働きます。野菜やきのこ類、海藻類など、歯ごたえのある食品を意識して献立に取り入れることも、虫歯予防につながります。
定期的な歯科検診の重要性
ご家庭での丁寧な歯磨きや食生活の管理はもちろん大切ですが、それだけでは防ぎきれない虫歯もあります。そこで重要になるのが、歯科医院での定期検診です。歯が生え始めたら、遅くとも1歳までには一度歯科医院を受診し、かかりつけ医を見つけることが推奨されています。
定期検診では、歯科医師や歯科衛生士が、ご家庭では見つけにくい小さな虫歯の兆候や歯並びの異常を早期に発見し、適切な処置やアドバイスを行います。また、プロによる歯のクリーニング(PMTC)で、普段の歯磨きでは落としきれない汚れを除去したり、フッ素塗布によって歯質を強化し、虫歯になりにくい歯にすることもできます。お子様の成長段階に応じた歯磨き指導も受けられるため、毎日のセルフケアの質を高めることにもつながります。
歯科医院は「歯が痛くなってから行く場所」ではなく、「虫歯を予防するために行く場所」という意識を持つことが、お子様の歯の健康を守る上で非常に重要です。定期的にプロの目でチェックしてもらうことで、虫歯の早期発見・早期治療につながり、お子様が将来にわたって健康な歯を維持するための土台を築くことができます。
まとめ:毎日の歯磨きで子供の歯の健康を育もう
ここまで、お子様の歯の健康を守るために必要な知識と具体的な方法についてご紹介してきました。乳歯は、永久歯の成長や顎の発達に欠かせない大切な役割を担っており、虫歯を放置すると将来の健康にまで影響を及ぼす可能性があります。そのため、毎日の丁寧な歯磨き習慣は、お子様の健やかな成長の土台を築く上で何よりも重要です。
歯磨きは、お子様の成長段階に合わせてケアの方法を変える必要があります。歯が生える前のガーゼケアから始まり、歯ブラシに慣れる練習、奥歯が生え始める頃からの仕上げ磨き、そして乳歯列が完成してからの歯磨き習慣化まで、それぞれの時期に応じた正しいアプローチが求められます。また、歯ブラシやフッ素配合歯磨き粉の選び方、保護者が行いやすい「寝かせ磨き」の姿勢、部位ごとの磨き方といった実践的なテクニックも、効果的な歯磨きには欠かせません。
お子様が歯磨きを嫌がる時期は、多くのご家庭で直面する課題です。しかし、歌や絵本、アプリを活用したり、保護者の方も一緒に歯磨きを楽しんだり、そして何よりも終わった後にたくさん褒めてあげたりすることで、歯磨きの時間を「嫌なこと」から「楽しいこと」へと変えていけるはずです。歯磨きだけでなく、だらだら食べを避ける食生活の工夫や、歯科医院での定期検診も虫歯予防には非常に効果的です。
お子様の歯のケアは、親御様にとって大変なことも多いかもしれませんが、この記事でご紹介した情報を参考に、焦らず、楽しみながら取り組んでいただければ幸いです。日々の歯磨きを通じて、お子様の歯の健康を育み、輝く笑顔と健やかな未来を守っていきましょう。お子様の成長を応援する気持ちで、前向きにケアを続けていくことが、何よりも大切です。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
高橋 衛 | Takahashi mamoru
岩手医科大学歯学部卒業後、岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座入局し、
医療法人 高橋衛歯科医院設立 理事長就任、MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS 開設
【所属】
・日本歯科医師会
・岩手県歯科医師会
・盛岡市歯科医師会
・歯科医師臨床研修指導歯科医
・岩手県保険医協会
・日本口腔外科学会
・日本口腔インプラント学会
・EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION
・AMERICAN ACADEMY PERIODONTOLOGY
・岩手医科大学歯学会
・デンタルコンセプト21 会員
・日本歯科東洋医学会
・JIADS Club 会員
・P.G.I Club 会員
・スピード矯正研究会 会員
・床矯正研究会 会員
・近代口腔科学研究会 会員
【略歴】
・岩手医科大学歯学部 卒業
・岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座 入局
・「高橋衛歯科医院」 開業
・「MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS」 開業
岩手県盛岡市の歯医者・歯科
『高橋衛歯科医院』
住所:岩手県盛岡市北天昌寺町7−10
TEL:019-645-6969